企業において、従業員が病気やけがなどで長期間働けなくなった場合、「休職」という制度が適用されることがあります。しかし、休職制度の運用を誤るとトラブルにつながることもあるため、適切な対応が求められます。本記事では、休職者対応の流れと注意点について詳しく解説します。
1. 休職制度とは?
休職とは、従業員が私傷病(業務外の病気やけが)などにより就業が困難な場合に、一時的に労働義務を免除する制度です。休職期間中は給与の支給が停止されることが一般的ですが、健康保険の傷病手当金を受給できる可能性があります。また、復職の際には医師の診断書を提出し、企業が安全配慮義務を果たすために適切な手続きを行う必要があります。労働基準法には明確な規定がないため、就業規則に基づいて運用されることが一般的です。ただし、企業には労働契約法第5条に基づく安全配慮義務があり、適切な休職制度の整備が求められます。
休職と傷病手当金の関係
休職中、従業員は賃金を受け取れないケースが多いため、健康保険の傷病手当金を活用することが可能です。傷病手当金は最長1年6か月支給されるため、休職期間とあわせて確認が必要です。
2. 休職者対応の流れ
(1) 本人からの申し出・診断書の提出
休職を希望する従業員から、医師の診断書を提出してもらいます。診断書には、病名や就業の可否、休職の必要期間が記載されていることを確認します。休職発令は会社の判断で行うことは可能ですが、不当な休職発令とされるリスクを避けるため、基本的には本人からの申し出を受ける形で運用するのが望ましいです。
(2) 休職開始の決定と通知
会社は診断書の内容をもとに休職の可否を判断し、休職が認められる場合は「休職通知」を正式に発行します。復職できない場合に休職期間満了退職の取り扱いをするためには、適正な手続きを経ることが不可欠です。休職の届け出のみを従業員に行わせ、正式な発令を行っていない企業も見られますが、その場合、休職期間満了退職が認められず、結果として不当解雇と判断されるリスクが高まります。
(3) 休職中のフォローと定期的な報告
休職中の従業員とは定期的に連絡を取り、病状の経過や復職の見込みについて報告を受けるようにします。具体的には、1か月に1回の面談やメール・電話での状況確認を行うことが望ましいですが、メンタルヘルス不調の場合は過度なプレッシャーとならないよう、慎重に対応することが必要です。
(4) 復職可否の判断
休職期間が終了する前に、医師の診断書をもとに復職の可否を判断します。
- 復職可能な場合:主治医の意見とともに産業医の判断を受け、復職可能と判断された場合は復職手続きを進めます。
- 復職困難な場合:休職期間満了時に復職が難しい場合、就業規則に基づき「休職満了退職」とするか、場合によっては「解雇」の判断を検討します。ただし、労働契約法第16条では、解雇には客観的に合理的な理由が必要であり、社会通念上相当であると認められることが求められます。過去の判例においても、休職期間満了による解雇が無効とされたケースがあるため、慎重な対応が必要です。解雇を検討する場合は、産業医の意見を踏まえた復職支援措置の実施や、退職勧奨を行うなどの手続きを適正に進めることが重要です。
3. 休職者対応の注意点
(1) 休職期間の上限を明確にする
休職期間は企業ごとに異なりますが、一般的には1か月~1年6か月程度が設定されています。期間が明確でないと、復職や退職の判断が曖昧になり、トラブルにつながる可能性があります。
(2) 休職理由の確認と就業規則の適用
休職は原則として私傷病が対象ですが、家庭の事情などで休職を希望するケースもあります。その場合、就業規則に沿った対応を徹底することが重要です。
(3) 復職判断の際の産業医の意見活用
復職判断は主治医の診断書だけでなく、会社側の安全配慮義務の観点から産業医の意見を取り入れることが望ましいです。特にメンタルヘルス不調の場合、復職後の業務負担を慎重に検討し、短時間勤務や業務内容の調整などの措置を講じることが望ましいです。
(4) 解雇リスクを避けるための適正手続き
休職期間満了後に復職が困難な場合、就業規則に基づいた適切な手続きを踏むことが重要です。特に「解雇」にあたる場合は、不当解雇とならないよう、合理的な理由の提示と十分な手続きを行う必要があります。解雇前には退職勧奨を検討し、産業医の意見を取り入れることも有効です。
まとめ
休職者対応は、従業員の健康と会社の運営を両立させる重要な課題です。休職制度を適切に運用することで、従業員の権利を守りながら、会社の業務継続にも配慮できます。本記事のポイントを参考に、自社の休職制度の見直しや対応の整備を進めてみてください。
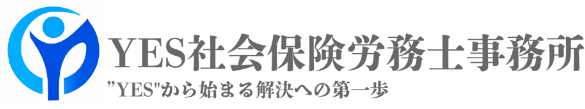
 2025年4月から開始!育児時短就業給付金について
2025年4月から開始!育児時短就業給付金について