中小企業の人事労務を支援する中で、こんな言葉をよく耳にします。
「うちはちゃんと就業規則がありますよ」
「前に社労士さんに作ってもらってそのまま使ってます」
でも、少し踏み込んで聞いてみると、
「社員の方はその内容を知っていますか?」という問いに
戸惑われることも少なくありません。
就業規則は、“ある”だけでは不十分です。
社員に周知されていなければ、法律上「効力を発揮しない」可能性があります。
この記事では、就業規則の法的な位置づけと、実務での落とし穴、
そして「活かせる就業規則」にするためのポイントについて、社労士の視点で解説します。
就業規則は「伝わっていてこそ」意味があります
労働基準法第106条には、以下のように定められています。
使用者は、就業規則その他これに準ずるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、備え付け、または書面や電子メール等で労働者に周知しなければならない。
つまり、「作成しただけ」では不十分で、会社として社員に就業規則を周知させることが求められます。
もちろん、「詳しく見せすぎると社員が権利ばかり主張するのでは…」と感じる経営者の方もいらっしゃいます。
ですが、適切に伝えられたルールこそが、社員との認識のズレを防ぎ、会社を守る“根拠”になります。
よくある「あるけど機能していない」就業規則
- 作ってから一度も見直していない
- 社員に配布していない、見たこともない
- 管理者ですら内容を把握していない
- 実際の運用と規則がズレている
このような状態では、いざというときに“盾”にならないどころか、
「こんなルール、初めて知った」と社員との信頼関係にも影響します。
運用されてこそ、就業規則は意味を持つ
就業規則は、「社員を縛るためのもの」ではなく、
会社と社員の双方が安心して働くための共通ルールです。
だからこそ、
- 実態に合っていること
- 社員がある程度は内容を理解していること
- 管理者自身も説明できること
が大切です。
法的に周知されていない就業規則は“効力を持たない”ことを忘れてはなりません。
まとめ:「あるだけ」では、守れない
「とりあえず作ってある」では、会社も社員も守れません。
就業規則は、定期的に見直し、必要な箇所をアップデートし、
社員との間で「共通認識」を持てる状態をつくることが大切です。
YES社会保険労務士事務所では、
実態に合った就業規則の整備から、社員説明会の実施、周知のサポートまで一貫して対応しています。
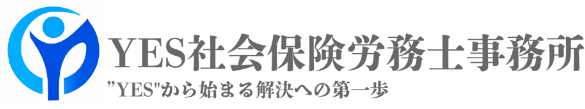
 労働条件通知書、出してますか?──社保の有無に関係なく“全員に必要”な理由とは
労働条件通知書、出してますか?──社保の有無に関係なく“全員に必要”な理由とは