契約満了だから更新しないだけ。
中小企業の現場では、こうした判断がよく見られます。
ですが実際には、契約が切れるからといって自由に契約を打ち切れるわけではありません。
法的に見ると、雇止めには慎重な対応が求められるケースが多くあります。
この記事では、雇止めに関するよくある誤解や、企業が気をつけたいポイントについてわかりやすく解説します。
雇止めが問題になる典型的なパターン
たとえ契約期間が満了する場合であっても、雇止めが解雇と同じように扱われることがあります。
とくに以下のような状況がある場合は、法的リスクが高まります。
・これまで何度も契約を更新してきた
・契約書に、更新の判断が会社にあることが曖昧に書かれている
・通算5年で無期転換の制度について説明や運用がされていない
・次回の更新があるかのような言動をとっていた
こうした場合、契約満了による雇止めであっても、労働者から不当と主張される可能性があります。
裁判でも問われる「期待するのが当然だったか」
雇止めがトラブルになるかどうかの一つの基準が、労働者が更新を期待するのが合理的だったかどうかです。
これは「雇用継続への期待権」と呼ばれることがあります。
例えば以下のような状況は、更新への期待が合理的だったと判断されやすいです。
・複数回の契約更新がなされていた
・正社員とほぼ同じ業務内容だった
・勤務評価に問題がなかった
・突然の雇止め通告だった
このような事情がある場合、たとえ形式的には契約社員でも、実質的には正社員に近いとみなされ、企業側の説明責任が問われる可能性があります。
企業ができる対策とは?
雇止めによるトラブルを防ぐには、日常の契約運用と事前準備の両方が重要です。
・契約書に更新の有無やその判断基準、更新上限などを明記する
・毎回更新時に本人との意思確認を行う
・評価記録や面談記録を残しておく
・無期転換ルールについて正確に伝え、運用ルールを整備しておく
・更新をしない場合は、できるだけ早い段階で説明を行う
このように、形式面と実務面の両方で記録や整理をしておくことで、万が一のトラブルに備えることができます。
まとめ:雇止めは「契約満了」で終わらせてはいけない
契約社員であっても、何度も更新を繰り返している場合や、正社員と同じように扱っている場合は、簡単に契約を打ち切ることができないケースがあります。
一見、契約満了で自然終了に見えるケースでも、慎重な運用が求められます。
「うちの契約社員の対応、大丈夫かな」と感じた方は、ぜひ一度、契約書の内容や契約更新の流れを見直してみてください。
YES社会保険労務士事務所では、契約社員・パートタイマーの制度設計や運用支援を行っています。
チェックだけでもお気軽にご相談ください。
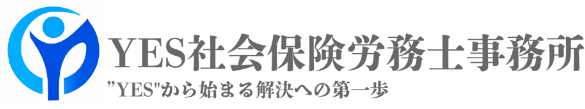
 ハラスメント対策・女性活躍推進に関する法改正が公布されました
ハラスメント対策・女性活躍推進に関する法改正が公布されました