「労働条件通知書って、正社員だけ出せばいいんですよね?」
「社会保険に入らないパートさんだから、出していません」
中小企業のご相談を受ける中で、こうした声を耳にすることがあります。
実はこれ、法律的には完全にNGです。
労働条件通知書の交付は、正社員・パート・アルバイト問わず、すべての労働者に義務づけられています。
この記事では、「なぜ必要なのか」「どんなリスクがあるのか」、そして実務での落とし穴や見直しのポイントまでを解説します。
労働条件通知書は“全員に”必要です
労働基準法第15条には、以下のように定められています。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この「労働者」には、正社員だけでなく、パート・アルバイト・有期契約社員も含まれます。
さらに、社会保険の加入の有無や、労働時間の長さも関係ありません。
「週2日勤務のアルバイトだから」「1日3時間勤務の方だから」といった理由で通知書を出さないのは、明確な違反です。
口頭説明だけではダメ?
「時給1,000円で、週3日くらいお願いね」
このような“口約束”で雇用を開始した結果、後からトラブルに発展するケースもあります。
- 「そんな条件で働くなんて聞いてない」
- 「交通費は出ると思っていた」
- 「勤務時間は自由じゃなかったんですか?」
書面で条件を明示しておくことで、こうした食い違いを防止できます。
労働条件通知書は、従業員の安心だけでなく、会社を守る“盾”にもなります。
書類の形式や電子化について
厚生労働省のモデル様式に沿って作成するのが一般的ですが、自社の実情に合わせた様式で問題ありません。
また、現在ではラウドシステムを用いた交付も可能です。
※ただし、労働者が「紙での交付を希望する」場合には、紙での提供が必要です。
加えて、厚労省のひな形をそのまま使用していても、実務では抜け漏れや誤解を生むケースが見られます。
たとえば、以下のような点が問題になりがちです。
- 雇用契約書との整合性が取れていない
- 試用期間の取扱いがあいまい
- 社会保険の加入条件や、契約更新有無の記載が不十分
そのため、実務に即した形で、専門家によるチェックを受けることをおすすめします。
テンプレートを「とりあえず使っている」状態のままだと、後に大きなトラブルを招く可能性があります。
まとめ:通知書は義務であり、トラブル予防策です
労働条件通知書は、法令上の義務であると同時に、従業員との信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐための重要なツールです。
「うちはちゃんと出せているだろうか」
「以前作った雛形のまま使っているが、今も通用するのか?」
そう感じられた方は、ぜひ一度ご相談ください。
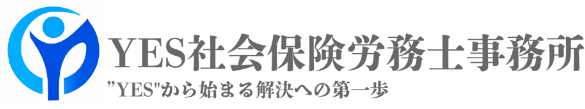
 採用でトラブルにならないために──就職差別につながるおそれのある14項目とは?
採用でトラブルにならないために──就職差別につながるおそれのある14項目とは?