「年俸制だから、残業代は発生しませんよね?」
中小企業の人事担当者や経営者の方から、こうしたご質問を受けることがあります。
たしかに年俸という言葉には、すべての給与が包括されている印象を受けがちです。
ですが、年俸制=残業代不要ではありません。むしろ適切に運用しなければ、未払いリスクが高くなる制度でもあります。
この記事では、年俸制に関するよくある誤解と、企業が気をつけるべきポイントについて解説します。
年俸制とは?月給制との違い
年俸制は、1年間の給与総額をあらかじめ定めておき、それを月割りで支給する制度です。
月給制との違いは、年単位で報酬設計をする点にあります。
ただし、年俸制を採用していても労働基準法が適用されることに変わりはなく、労働時間の管理、残業代の支払い義務は当然に発生します。
「年俸制にしたから残業代は払わなくていい」というのは誤った理解です。
管理職・裁量労働制とは別物です
「うちは年俸制だから、管理職扱いで残業代なし」と考えてしまうケースもありますが、
年俸制と「管理監督者」や「裁量労働制」はまったくの別制度です。
・管理監督者とは、経営に近い裁量を持ち、労働時間の規制が及ばない立場
・裁量労働制は、業務の遂行手段や時間配分を労働者に委ねる制度(導入要件は非常に厳しい)
つまり、年俸制というだけで残業代の支払い義務がなくなることはありません。
賞与扱いの年俸分割に注意
年俸制では、12ヶ月で単純に割るのではなく、14分割や16分割で支給するケースもあります。
たとえば「年俸を12ヶ月+賞与2ヶ月分で分割する」ような設計です。
この場合、賞与相当分であっても、あらかじめ金額が確定しているため、割増賃金の算定基礎に含める必要があります。
つまり、実質的には毎月分割しているだけであれば「賞与」という名目であっても、残業代の基礎賃金に含めるべきという判断がされることがあります。
年俸制を適切に運用するために
年俸制をトラブルなく運用するには、以下の点を押さえることが重要です。
・年俸制を採用していても、労働時間を把握し、残業が発生すれば割増賃金を支払う
・「管理職」「年俸制」などの名称だけで、労基法上の免除はされない
・年俸を複数回に分けて支給している場合、その賞与部分も含めて残業代の算定基礎に含まれる可能性がある
・就業規則や契約書での報酬の取り扱いを明確に記載する
まとめ:年俸制でも“労働時間の対価”を忘れずに
年俸制は、給与設計の自由度が高く、制度として合理性もあります。
しかし、「年俸制だから大丈夫」という思い込みで制度設計を誤ると、未払い残業代や訴訟リスクにつながることもあります。
報酬の内訳や支給形態、労働時間との整合性をしっかり確認し、法的に問題のない制度設計を行うことが大切です。
「うちの年俸制、大丈夫だろうか?」と感じた方は、一度、契約書や支給方法を見直してみてください。
YES社会保険労務士事務所では、年俸制・残業代の適切な運用設計のサポートも行っております。
制度のチェックだけでも対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
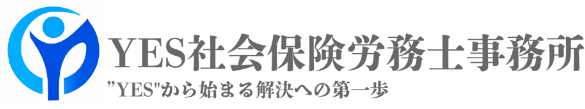
 その雇止め、本当に問題なし?中小企業が見落としがちな落とし穴
その雇止め、本当に問題なし?中小企業が見落としがちな落とし穴